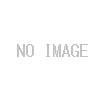<div/>こんにちは! LINKデータベースシステムです。
本日は、本システムに御アクセスいただき、誠にありがとうございます。
どのようなご用件でしょう?<div/>
入力[Fragment File の閲覧]
<div/>LINKシークレットデータ Fragment File の参照ですね。
Fragment File の閲覧には管理者権限が必要です。パスワードを入力してください。<div/>
入力[*************]
<div/>データサーバよりファイル情報をロードしています。
セキュリティの安全性をチェックしています。
リソースを確認しています。
しばらくお待ちください…<div/>
*
男が夜更けに突然騒ぎ出し、その狂ったような声は地下の石畳で眠る拓弥の耳にも届いた。ちょうど浅い眠りから覚めて用を足し、寝床へと戻る帰りの階段で、まだ施設の部屋割りに慣れていない拓弥にとってはある種、地上の妖怪による咆哮であるかのように思えた。
誰が何を叫んでいるのか、拓弥にはまったく判断しかねたが、明らかに知っている声ではあった。しかし顔が浮かばない。
そんなことを考えているうちに、おそらく今の今まで地上で寝ていたであろう誰かが、
「おい!」、「うるせえ!」などと、脳の限界ともいうべき罵詈を『眠りを妨げた薬物中毒者』というパブリックエネミーに対して一斉に浴びせる。ただし、そいつと同室にいる奴に限っては怒るというより、一刻も早くその場を収めようと、妄言が速射砲のごとく繰り出されるその悪しき口を力いっぱいに封じ込めたり、洗濯のしすぎで若干カバーが灰色がかった枕を頭目がけて投げつけたり、あるいは常日頃から怒りに飢えた男たちが部屋に雪崩れ込んでくることを止められないと悟り、トイレや別室に逃げ込んだりする。拓弥はここに来てまだ三週間しか経っていない身だが、すでにこういうことは何度か経験している。
地上には多くの人がいて、どこの部屋も誰かとの相部屋になっているが、地下はすべて一人部屋だ。ここに来た初日に聞いたが、地下の部屋にいる人間は基本的に超が付くほど大人しい感じの奴か、新しく入ってきてまだ人間性の十分に査定が済んでいない奴かのどちらからしい。拓弥は比較的大人しいタイプではあるが、それはあくまで誤差の範囲でしかなく、人が集まればたいていのことは楽しく感じるし、社交性も高くはないが致命的に欠落してはいない。そういうことから推測するに、拓弥は後者の場合だった。だから時が経てば、拓弥も地上へと部屋を移されるのだろう。
食堂やロビーや休憩室などはすべて地上にある。地下にあって地上にないものといえば、コンクリートに囲まれているために夏でも冷たくて冷房がいらないという環境くらいのものだ。
地下はもともとコンクリートの地盤だったものが、人が増えて施設に収まりきらなくなることを見越して『所長』が業者を介さずに、施設にいる人間だけで作らせたというものだった。しかしそんな突貫工事で出来た空間であるにも関わらず、地下での暮らしは快適そのものだった。とはいえさすがに下水道や上水道を整備することはできなかったようで、トイレは地上のものを使うしかない。トイレは一応男女で分かれているが、今現在この施設に女は一人もいない。半年前には女が三人いたというのを盗み聞きしたことがあるが、どういった経緯で女がこんなところに来るのか、拓弥には分からなかった。
そんなことを考えているうちに、いよいよ騒がしい夜になってきた。ドンドンと男たちが地面を乱暴に踏みつける音と、怒りや怠惰といった感情のこもった有象無象の声とが地下に響く。その大半は聞くに堪えない言葉の類だ。皆眠っていたのだろう。
地上は四階まであって、エレベーターは無い。だから階を移動するときは皆、コンクリートの階段を使う。事実今も、誰かが階段を駆け上っていく音が絶え間なく聞こえているのだ。そしてだんだんと遠くなっていく足音で、男たちが四階を目指していることを知る。騒ぎの発端となった男はまだ理解不能な言語で叫び続けている。地上のどこかでガタンと大きい音がした。それは椅子が倒れる音だ。あるいは電気スタンドが倒れる音だ。あるいはドアが勢いよく開け放たれる音だ。
そのとき、拓弥は猛スピードで階段を駆け上がる誰かとすれ違った。それは踊り場の死角からいきなり現れたため危うくぶつかりそうになったが、なんとか身をよじって拓弥は男との接触を回避した。あいつも野次馬に行くのだろうか。決して戦いには参加せず、傍観して冷笑する観衆。そんな人間のことを想像すると、吐き気のする思いだ。不快感を覚えながら、拓弥はコンクリートの階段を下りて、自分の戻るべき部屋へと向かった。
皆本当に戦いたがっているのだろうか。横になってそんなことを考える。俺が本当にしたいことは施設の内ゲバをぼうっと地下から観測することか。俺はもっと映画を見たり、ギターをやったり、女とセックスしたりするべきなのだ。ここに来る前は映画を吐くほど見ていたし、指の骨がすり減るぐらいにギターを弾いていた。セックスだってそれなりにできていた気がする。しかし今はどうだ。こんな所にいて、いったい何になる? 自分の過去と未来が、同時に押し潰されていくのを感じながら生きることに、いったい何の意味がある? 俺以外の人間はみんな人生を諦めてしまったのだろうか。そして俺もいつかそうなるのだろうか。拓弥は部屋の薄い毛布の上に寝転んで、そんなことを考える。
地上から聞こえてくる、ドタバタという表現では収まりのきかない音が次第に強まってきた。地上では一体何が起こっているのだろうか。こういう時はだいたい腹を殴ったりして黙らせるのが定番だが、たまに激高した男が家具で頭を狙ったり、窓から突き落そうとするケースもある。これも盗み聞きしたことだが、施設に入って長い古参の言う事だから間違いなくそういうことはあったのだ。ここにはたくさん麻薬中毒者がいる。だから、身を守るためにもクスリはやらない方がいい。これは入ってきてからすぐに、歓迎もなしに言われたことだ。
ゆるやかな坂道の住宅街を抜けた先にある小さな商社ビルの屋上から少年が飛び降りた。ビルの高さはおよそ三十メートルで、もちろん少年は即死だった。しかし奇怪なことに、少年の身元は誰にも分からないのだった。分かっているのは少年の遺留品のスマホにインストールされていたSNSアプリ『LINK』の『黒』というハンドルネームと、不特定多数のメールアドレスに『黒い花束が風に乗って、あらゆる世界に秘密のメッセージを届ける。』という文言のメールを大量に送信していた痕跡だけ。
そしておれに分かることは、少年の精神がこの世界から消えたということだけだ。そして少年の肉体が解剖される前に忽然と消えてしまったということ。検死の直前、死体を安置しておく部屋で少年の肉体は、消失した。この事象の理屈をおれに聞かれても困るが、かといっておれ以外の誰かに同じ問いを投げかけてもやはり困らせるだけだ。理論上ではありえないことが起きた。それ以外のことをおれは何も知らない。
おれはデスクに座る。それからダイナブックのノートPCで『LINK』を起動し、『黒』のプロフィールにアクセスする。
『黒』『フォロワー:0』『フォロー:0』『ID:7438217224』『まだ紹介文が設定されていません』の表示。プロフィールアイコンは初期アイコンというわけではなく真っ黒で、おれは何だか威圧的な印象を抱く。
おれは主に海外サッカーの情報を追いかけるツールとして『LINK』を使っている。だからこういうインターネットの深海に潜んでいるようなアカウントを普段目にする機会もなく、おれとしては何のために存在しているのかわからないアカウントという程度の印象しかなかった。
おれは『黒』のページを閉じ、少しネットサーフィンしていたところで見つけたバルセロナの移籍情報をチェックしてからノートPCの電源を切り、冷めきったコンビニ弁当で夕飯を済ませた。
誰もいない待合室で白い部屋の天井を見ていたら受付のお姉さんに名前を呼ばれた。診察室に通されて椅子に座ったけれど、先生の姿が見当たらない。看護師のひとは私が座るとすぐ診察室から出て行った。私はいつも通りに薬を貰えればそれでいいので、何分でも先生と処方箋を待つつもりでいたのだが、先生は一向に現れないどころか誰も何も伝えに来ない。それでも私はぼけっと座って先生を待ち続けた。私が自分で病院に行って薬を貰って帰ってきたら今日はケーキが食べられる。なんのケーキだろう。紅茶はいれてくれるのだろうか。そういうことを考えていると、さらに口がケーキを欲して、ケーキでなくとも砂糖で構成された甘いものを口に入れてやりたくなる。たまらなくなって、私は診察室の壁掛け時計を見た。そこで、私が二時間以上も診察室で待たされているということにようやく気がついた。そこで私は自分が夢を見ているのだと気がついた。現実の世界はもっと簡単にカウンセリングを受けて薬を貰える。だとしたら自分が夢の世界に留まる理由はなく、私はどこに向かう必要も何を待つ必要もないのだと知った。しかし何だろう、湖に反射した月の光を見ているようなこの気持ちは…
『そろそろ寝ようと思うんだけど』
画面の中で各々根気強くクエストをこなす仲間たちに向けて、ハンドルネーム『ぴかちゅー』は『LINK』のゲーム内チャットで文章を打ち込む。
「あーもうおやす?」
画面の向こう側からリアルタイムに『鬼斗』の声が聞こえた。パソコンのディスプレイ上の通話画面にはハンドルネーム『ぴかちゅー』と『鬼斗』、『パンドラ政府』『凛々の明星』の名が連なっている。『ぴかちゅー』は昨日から喉を痛めているため、普段は通話で喋りながらゲームをしているのだがそのスタイルを一時的に折り、意思の疎通をチャットに任せている。
『うん』
『ねるわ』
『おやすみ』
「おやすみー」
それには答えず、ハンドルネーム『ぴかちゅー』こと中尾郁は通話から退出する。画面上に『3人が通話しています』の文字。朝起きてから充電しっぱなしだったワイヤレスイヤホンの白いケースを充電器から切り離して、イヤホンを取り出して両耳にはめる。今日は何のASMRを聞きながら寝ようかとおすすめ動画を漁っていると、実に昼ぶりに携帯が振動した。
『新着メールがあります。』の通知をタップして、顔認証を突破する。最近買い替えたスマホは部屋がよほど真っ暗でもない限り、『ぴかちゅー』の顔を捉えてすばやくロックを解除することができる。
『From:blackalice@vividmailer.jp』『件名:無題』
『あなたはこのメールを見ました。つまり、あなたの脳内にわたしという存在が確かに生まれたのです。わたしがどんな人間なのかはまだ分からないと思いますが、それでもわたしの存在があなたの中に生まれたことは揺るがない事実。わたしはここから先、もっと多くの人の中に偏在していきます。その時にまた会いましょう。』
これは大した意味のないメールだと『ぴかちゅー』は即座に判断し、メールフォルダから削除しようと思ったが、なにぶんメーラーアプリを起動したのがかなり久しぶりなので、どう削除するのかわからずに戸惑ってしまった。それにしても、何でこのメールは迷惑メールフォルダに入っていないのだろうか。『LINK』のゲーム内メッセージをメールで通知しない設定にしてからというもの、このアプリは完全に容量を食うだけのジャンクアプリと化していた。
就活情報のメールや何となくで受信設定をオンにしているメールマガジンの通知は来ない。途端に歯磨きや入浴なども面倒になり、朝起きたときそのままのフォルムで丸まっていたグレーの掛け布団を片手で引っ張ってきて、寝室も敷き布団もない部屋の片隅で音の鳴らないイヤホンをしたままなし崩し的に横になる。
わたしの十八歳の誕生日に、母は行方不明になった。
母は地元の小さな小学校で教員として昔から働いていたが、毎年わたしの誕生日には絶対に休みを取って、それから近所の『フォンテーヌ』というケーキ屋でわたしの好きなイチゴのたっぷり乗ったホールケーキを買って帰ってくる。
わたしは一人っ子で、ほかに家族もいなかったから、誕生日のケーキはだいたい余った。わたしは甘いものはとても好きだが、たくさん食べると気分が悪くなってしまうから、そんなに多くは食べられなかった。
わたしは母に誕生日プレゼントをもらったことがない。そのかわり、父から誕生日プレゼントを毎年もらっていた。十七歳の誕生日のときは、小さいビデオカメラをもらった。母がまだいた頃だった。
「私よりも、お父さんのほうが癒奈のことをわかってると思うから」
と母はことあるごとに言って、父にプレゼントを買わせたが、もらったもので素直に嬉しいと思ったのは二年に一回か三年に一回ぐらいのことで、去年もらったビデオカメラも、わたしには使い方がよくわからず、そもそも動画はスマホで撮っていたから、わたしがそのビデオカメラを使うことはほとんどなかった。
その日も、母は『フォンテーヌ』へ癒奈の誕生日ケーキを買いに行くと言って、黒いヒールを履いて外に出た。わたしも父も、母が家にケーキを買って帰ってくると当たり前のように思っていたし、母の帰りが遅くても、それは『フォンテーヌ』へ行く途中でたまたま知り合いに会って、それで話が長引いているんだとか、あるいは『フォンテーヌ』のケーキが売り切れていて、ほかのケーキ屋を探しているのだとか、そういうことをわたしは思ったし、ましてやこの状況で母が帰ってこないだなんて想像もつかなかったし、したくもなかった。
わたしが学校から家に帰ってきたときに、母はまだ家にいた。わたしはそっと冷蔵庫を開けて、ケーキの在り処を探したが、冷蔵庫にケーキはなかった。わたしはそれで少しがっかりしたが、それを見た母は
「ケーキなら、あとで買ってくるからね」
と優しく言い、わたしを喜ばせた。そして、
「癒奈が成人になる日のケーキは、とても豪華なものにしようと思ってるんだ」
と母がいつか言っていたことを思い出して、思わず頬がゆるんだ。
母が出かけてから、父が帰ってきた。父は小さな文房具メーカーに勤める営業部のサラリーマンで、秋の時期はとても忙しいのだといつも言っている。だけどやっぱり、父もわたしの誕生日には毎年有給を取ってくれていて、だからわたしの誕生日には必ず家族全員がそろっていた。
父は、スモークした合鴨をコンビニで買ってきていた。わたしは鴨肉なんて食べたことがなかったから、とてもワクワクしていた。
父はサラリーマンなのにお酒がまったく飲めなくて、ときどき帰りが遅れる会社の飲み会ではいつもお茶ばかり飲んでいるのだと愚痴をこぼしていたけど、大学時代はすごく酒が好きだったらしい。アルバムにも、父が外国のどこかのバーでショットを一気飲みしている写真があった。父の隣でアメリカ人が白目をむいて倒れているところを見ると、飲み比べをしていたに違いない。
わたしの友達にも、小さいころからメロンを食べすぎて嫌いになってしまったお金持ちの家の女の子がいて、すごくかわいそうだなあと思う。その子はわたしの母とも面識があって、面識があるどころか仲がよくて、前にわたしの家に来たとき、癒奈のお母さんが作るお味噌汁は天下一品だと褒めちぎっていた。
わたしは小さい頃、ニンジンがとても苦手で、給食でもニンジンだけは毎回綺麗に残していた。だから、母が味噌汁にニンジンを入れるのが嫌で、そのことを言ったのに母はそれを無視して味噌汁にニンジンを入れて、どうしてもニンジンを食べたくないのと土下座までして頼み込んでも、母は味噌汁にニンジンを入れ続けた。どうしても両親が買い物に行けなくて、ニンジンと大根しか入っていない味噌汁が食卓に並んだ時、わたしは泣いてしまった。小学三年生にもなって、ニンジンで泣いてしまうようなわたしを母は叱らなかったが、味噌汁からニンジンが取り除かれることはなかった。
その甲斐あってか、わたしはどんどんニンジンに慣れていって、中学に入る頃にはもうニンジンを見ても苦い顔をしなくなっていた。それを見た父は、娘の頑張りと母の執念の両方を褒めた。
母がいなくなってから、父は元気をなくした。わたしもなんか元気ないねと友達や先生から言われた。母がいなくなったことを、わたしは友達に言わなかった。担任の先生には父が説明してくれた。
母がいなくなったことに、父は悲しんでいた。それまでずっと仲良く一緒に暮らしてきたのに、よりによって娘が成人を迎える誕生日に失踪するだなんて、普通では考えられないことだ。
母がどこに行ったのか、わたしにはわからなかった。見当もつかなかった。
はじめ、母の帰りが遅いということに気づいたのはわたしではなく父だった。すでに母が家を出てから三時間あまりが経っていて、言われてみれば確かに母の帰りはとても遅かった。しかし、そのときのわたしはまさか母が行方不明になるなんて思っていなかったから、そこまで心配もしていなかった。
夜も十一時を回った頃、ようやくわたしにも心配の気持ちが芽生え始めた頃、父は母に何度も電話をかけていた。そのすべてに応答がなく、ただいま電話に出ることができません、と言われて電話が切れるたびに父はため息をついて、それからまた母に電話をかける、ということを日付が変わるまで繰り返した。わたしは物心がついてからはじめて、誕生日にケーキを食べなかった。
次の日、父は警察に相談した。わたしも学校帰りに警察署に行って、二人の男性警察官に母のことをいろいろ聞かれて、一時間ぐらいずっとしゃべっていた。
事情聴取が終わってロビーに行くと、父がいた。放心したような表情で、夕方のニュース番組を見ていた。父はとてもショックを受けていた。わたしもショックを受けていた。しかし、それは悲しむというような感じではなく、むしろ悲しむ隙もないぐらいにあっさりと、母はわたしたちの前から消えてしまった。
倉庫とは名ばかりの、ただただ暗くて一面ホコリしかないような汚いプレハブ小屋に俺たちはよく集まる。
俺たちの夜の遊び場と言えばこの倉庫かレールウェイの高架下で、このあたりのゲーセンではだいたい出禁を食らったから最近は暇を潰す手段が減った。いつもだったら、この密閉された薄暗い空間であてもなくタバコを吸うか、ひたすらにLSDを飲みまくるかのどっちかだったが、今日はそのどちらでもなく、名古屋のロックフェスに行こうとか誰々が結愛に嫌われたとかそんな感じの話ばっかりしていて、久しぶりにサッカーでもやろうかと俺がなんとなく言ったら案外みんな賛同したが、誰ひとり本気でやりたがっているわけではないことを瞬時に理解してやっぱりいいやと言う。
皆がくだらない話に盛り上がっていればいるほど、俺は眠くなる。そういうときはアパートの部屋にあるモデルガンのことを考える。本物のこいつを万博会場とか空港の入口でぶっ放すところを想像して無理やり気持ちを立てる。
皆、やることがなくなると破滅に突き進むかのごとく酒を飲んで騒ぐが、俺からしたら酒なんか飲んでもさらに眠くなるだけだ。結論から言うとそれはまったく間違っていなくて、ひとしきり騒いで叫んでからみんな俺よりも早くスタミナ切れで爆睡してしまう。そういうことが何十回もあった。風船を針で思い切り突き刺してやりたくなるような気持ちを抑えて、窓のない小屋の扉をそっと開けて鈍い輝きの星空を眺める。
またトラックに乗りたい、と思う。三年前に居眠り運転で追突事故を起こして今は普通免許ですら無免だ。あの頃はよかった。時間はないけど金はそこそこにあって、かわいい彼女もいて、極限まで腹を減らして車内のわずかな空き時間に食う飯はなんだって美味かった。カップラーメンでも汁は全部飲み、おにぎりのフィルムに張り付いた海苔すらも引っぺがして口に入れていたあの頃だ。
中学生のころはよく海岸通りを歩いていた。時々通り過ぎるディーゼルトラックが起こすあの風に心惹かれて、俺はトラックドライバーになった。免許取得の試験には二回落ちた。一回目は壁を殴って、二回目は女を殴った。
俺はこっぴどい目に遭わないと人生の態度を改めようとしないのに、それなのにひどい目に遭った時はすぐに暴力を振るう。拳があれば人間はなんでもできる。人を殺せる。人の価値を奪える。俺の前に立ちふさがるものはすべて暴力で片づける。今はそんなものは俺の前にない。だからこの拳も使われないまま眠っている。俺は足元の雑草を踏み潰して、冷たい空気の中でポケットからメンソールタバコの箱とジッポーを取り出す。
やられる前にやられるしかない。タバコに点火。ジッポーとタバコの箱をポケットにしまい、いつか訪れる戦いに備えて、タバコをくわえたまま孤独にシャドウを始めた。相手は人ではなくトラックだ。俺のパンチでトラックをスクラップにする。夢と過去の鎖をぶち壊して生涯を終わらせる。ボクシングなんかやってるやつはその時点で恵まれてるんだ。俺には一体何がある?
俺は単調な拳の反復の中で、怒りと決意を爆発させたような雄叫びをあげながら、もうすぐ夜が明けるなと思った。
まだなの、と私はかなりイライラしながら時計を見る。三か月前から今日のことばかりを考えて、昨日どころか先週ごろからずっとソワソワしていたのだ。それほどに楽しみにしていたのに、開始予定時刻から三十分以上経っても講演会は一向に始まる気配を見せない。
入場開始時間の二十分前に誰よりも早く着いて、はやる気持ちを必死に抑えながらロビーで粛々と経営学の本を読み流していた私だからこそ、その気持ちが強くなるのかもしれない。
しかし事実、講演会を聞きに来たその場のほぼ全員が、司会の「しばらくお待ちください」という苦し紛れの釈明に対して明らかに苛立っていた。演者の準備に時間がかかっているのか、はたまたまだ到着していないのか、そういった仔細を詳らかにすることなく、ただただ免罪符のように五分おきに発せられるその定型句は間違いなく百人中九十九人を苛立たせる性質のものだった。
壇上には『井上肇の講演会 ~現代社会における哲学の意義と誤った開拓の果て~』と書かれた横断幕とふたつの講壇、ひとつはステージ端の司会用で、もうひとつはステージの中心に妙に自信ありげに配置された『先生』用のものだ。
この瞬間にまた一分の遅延が発生している。そう思った瞬間、突如ホール会場に司会の声が響いた。
「えー、誠に勝手ではありますが、『井上肇の講演会 ~現代社会における哲学の意義と誤った開拓の果て~』については中止ということにさせていただこうと思います」
瞬間、頭に血が上った。どこまでもこの司会は無能だ。言葉遣いがまるでなっていないどころか、中止の理由すら伝えなだなんて、教養面でも人徳面でもどうかしている。事実、みんなそのようなことを思ったのだろう、一瞬で会場は大いなるざわめきを見せ始め、それは不特定多数による「どういうこと!?」や「理由は!?」という声もにわかに聞き取ることができるくらいだ。
突然の知らせに驚く聴衆とは真逆に、司会は処置なしといった顔でマイクを置いてステージの裏へと消えた。ただ残された私やその他の人間は、怒りよりも状況の意味不明さに戸惑っているような様子であった。殊に私の横に座っていた見ず知らずの女は、軽いパニック状態に陥ったためか撮影禁止のホール内でインスタライブを始めるという奇行に走った。
オーディエンスの資格を失った人間たちによる抗議と戸惑いのミックスした会場。その壇上にひとりの人間が現れた瞬間、会場に儚い静寂が訪れる。しかしそれは司会でもなければ『先生』でもない、青を基調とした作業服を身にまとった男の作業員だった。今目の前で起きている事態の更なる意味不明さに困惑している私を置き去りにして、作業員は軽くお辞儀をしてから一度舞台裏に戻り、すぐに布に包まれた四角い箱のような何かを台車で運搬してきた。
<title>生前の記憶の欠片。_
母がいなくなってから一週間が経っても、母を探す手がかりは見つからなかった。事件とも事故とも言い切れません、と警察にも言われて、それで父はさらにショックを受けていた。
母が失踪してから、父は一週間仕事を休んでいたが、その次の週からは会社に行くようになった。わたしは学校に休まず行って、そのたびになんか元気ないねと友達に言われた。先生はわたしに気を遣って、授業であまりわたしのことを当てないようにしてくれていた。
そして、わたしの誕生日から二週間が経った。父は親戚に母が失踪したことを電話で伝えた。わたしもそれを聞いていた。父の口調から、焦りと悲しみがとても伝わってきて、わたしも辛い気持ちになった。
だいたいの親戚は父に対して同情を示していたが、叔父だけは違った。母が失踪したのは父のせいだと、最初から決めつけてかかった。叔父との電話で、父はずっと謝っていた。わたしはそれに腹が立って、叔父に文句を言おうと父に提案したが、父はそれに賛同しなかった。
「つらい時に、誰かを責めたってしょうがないじゃないか」
と父は言った。わたしがつらいのはほとんど叔父のせいだったので、わたしは父の意見に納得しなかったが、どちらにせよ、叔父の連絡先も住所もわたしは知らないので、直接の文句のつけようがなかった。
母が失踪したのだということを、わたしは友達にまだ話していなかった。話そうと思ったことは何回かあった。しかし、話したから何になるのだ、としかわたしには思えなかった。話したら母は帰ってくるのか、母は見つかるのか。そういったことばかりを考えているうちに、わたしはいつしか母の失踪をまわりに話すタイミングを失ってしまっていた。
母のいなくなった食卓は、とてもさびしいものだった。いつも料理は母が作っていた。父は料理が得意ではなかったが、わたしはもっと得意じゃなかった。だから、料理は父が作ることになった。ただでさえ忙しいのに、心労に振り回されて、その上家事もしなければならない父がとても不憫で、わたしは炊事以外の家事を率先してやるようになった。
わたしは、特に両親から離れたいとは思っていなかった。進学して、一人暮らしがしたいとは思っていたが、別に家から通うことにも文句はなかった。わたしが母から離れたいと思っていて、それに母が気づいたから失踪した、そんな感じでうまく自分の中で母の失踪を片付けることができたら、それはそれでまだマシだった。
しかし、母は突然いなくなった。理由も告げず、ただわたしの誕生日ケーキを買いに行くという、幸福なことを言って、いなくなった。ケーキを買いに行く。去り際のセリフに、母がそんなことを言うだろうか。
せめて、これが事件なのか事故なのか、それだけでもわたしは知りたかった。それさえわかれば、母のゆくえがどこであろうと、自分なりになんとか納得のいく答えを作れると思ったからだ。しかし、母の失踪にはそういった脈絡というものがなく、だからわたしも父も、母の失踪に納得できないまま時間だけが過ぎていった。
ある日、今日は残業して帰ると父からメッセージが入った。その時のわたしはすべての課題を終えて、時間だけが余っていた。わたしは階段を上がって、自分の部屋に行こうとしたが、ふと方向を変えて、母の部屋へと向かった。
わたしは母の部屋にひとりで入ったことがない。一年ぐらい前に、部屋の電球を交換してくれと母に言われ、その時訪れたきりだ。
母の部屋は、いわゆる書斎というほどではないが、それなりに本棚がたくさんあって、だいたいわたしの知らない海外の小説が、綺麗にずらっと並んでいた。
母の部屋にも、父の部屋にも、わたしはひとりで入ったことがなかった。入る理由がなかった。でも今は違う。母がなぜ失踪したのか、というヒントが得られるとは微塵も思っていなかったが、わたしの知らない母が、そこにはいる気がした。
ドアには鍵がかかっていなかった。母の部屋も父の部屋も、いちおう鍵をかけることができるようになっているが、別に鍵をかける必要がないからと言って、結局誰でもドアを開けられるようになっていた。わたしの知らないところで、父と母は互いの部屋に出入りしたのかもしれない。そんなことを考えながら、わたしは母の部屋に入った。
カーテンは全部閉まっていて、部屋は薄暗かった。ドアのそばにあった電気のスイッチを人差し指でなんとか押して、部屋の電気をつけた。オレンジ色の光が部屋を包んだ。
母の部屋は、とても綺麗に片付いていた。本棚以外のものはほとんど部屋になくて、壁に向いたデスクと小さなゴミ箱、それから古い扇風機があるだけだった。とてもあっさりとした部屋で、当たり前だが母の失踪の手がかりのようなものはないように思われた。
白いデスクの上には、一台のノートパソコンと万年筆、そしてペン立て、海の波の写真が印刷されたうちわが置かれていた。二階の寝室以外の部屋にはエアコンがついていなかったので、わたしも夏はたいていリビングにいたが、母は扇風機やうちわを使ってなんとか暑さをしのいでいたのだろう。そういえば、父の部屋にも確か扇風機があったような気がする。
わたしは壁を見回した。壁には花の絵のカレンダーがかかっていた。母がいなくなった月からそれがめくられていないことにわたしは気づいて、何だかとても悲しい気持ちになってしまった。
わたしは少し考えてから、母のデスクに座った。何となく座り心地の悪い椅子で、これに母は座っていたのかと思った。リビングの椅子も、わたしの部屋の椅子も、こんなに座り心地は悪くないはずだ。
わたしは母のデスクの引き出しを開けてみた。引き出しには潰れた薬局のポイントカードだけが入っていて、何となく無駄な使い方をしているなと思った。
そして、ノートパソコンが目に入る。見たことのないものだった。父親の部屋にも、パソコンがあったような気がするけど、それは確かデスクトップパソコンだ。父親のパソコンはMacだったが、このノートパソコンがどこのメーカーのものなのか、わたしにはわからなかった。そういえば、パソコンを組み立てるのが趣味の男がクラスにいたが、そういう趣味が母にもあったのだろうか。
ノートパソコンの色は真っ黒で、何というか、母の性格とは合っていないような気がした。母は金属質なものが好きで、だから携帯もメタリックシルバーの色を選んだのだと言っていた。そんな母が、シルバーのデザインではなく、プラスチックの黒のデザインのものを選ぶだろうかと思ったが、母は案外、外面よりも機能面を重視するような気もした。
壁のコンセントは何とも繋がっていなくて、ノートパソコンの本体からはだらりと黒い電源コードが伸びている。おそらく、最後に使ったときにコードを外したものがそのままになっているのだろう。父なら、こういうケーブルは透明な結束バンドで結んで、まとめて綺麗にしまっておくだろう。
母のノートパソコンには、どんなソフトが入っているのだろう。わたしは、何となくそんなことを思った。さらに言えば、母はこのノートパソコンで何をしていたのだろう。仕事で使う書類などを作っていたのだろうか。つまりこれは仕事用のノートパソコンなのだろうか。しかしそんな話は聞いたことがない。母の仕事用のパソコンは小学校の職員室にあるはずだ。だとしたら、このノートパソコンは趣味用ということになるのだろうか。
そんなことを考えながら、わたしは〔POWER〕と書かれたスイッチの電源を押した。しかし、電源はつかない。なぜだろうと考えているうちに、そういえば電源コードが繋がっていなかった、とわたしは思い出した。だが、それ以前に、なぜわたしは母のノートパソコンの電源を入れようと思ったのだろう。自分でもよくわからなかった。
家族とはいえ、人のノートパソコンに無断で電源を入れるというのは良くないことだ。そのことはわたしにもわかっていた。しかし、娘の十八歳の誕生日に何も言わずに失踪してしまうということの方が、わたしには異常に思えた。事件だったのか、事故だったのかはわからない。ただ、まだ母は見つかっていない。それだけが事実だ。
わたしは少し考えたあと、決心して、電源ケーブルをコンセントにしっかりと差し込んだ。そして〔POWER〕のスイッチを押す。しかし電源がつかなかったので、今度は〔POWER〕を長押ししてみた。すると、キーボードの上にあった電源ランプが青く光った。
そして、自動的にモニターに電源が入る。電源を入れる前の真っ黒な液晶画面から、薄い黒の画面に変わる。わたしは思わず唾を飲み込んだ。静かな部屋と、わたしの頭の中に、母のノートパソコンの内部で何かファンのようなものが稼働する音がしつこく響く。それはまるで、母の内蔵から今まさに鳴っている音であるかのように感じられた。
モニターが段々と明るくなっていき、画面の中央でくるくると白い円のようなものが回っている様子が映る。起動に時間がかかるタイプのノートパソコンなのだろうか。母はこのノートパソコンをどこで買ったのだろうか。母はいつこのノートパソコンを買ったのだろうか。少なくとも、わたしが母と電球を取り替えた時には、このノートパソコンはなかった。そういうことを考えていると、モニター上の白い円が消えて、システマティックな白文字の英文が画面にあふれて、そしてすぐに消える。
わたしはモニターを見ながら、こんなことをして何になるのだろうと思い始めていた。父がこのことを知ったら、わたしは叱られるのかもしれない。母は、たぶん許してくれる。そんな気がした。
そしてモニターからはすべての文字が消えて、それから一瞬、画面がホワイトアウトした。それにびっくりして、わたしは思わず声をあげそうになる。それから、
[あなたは誰ですか]
…………?
白っぽい画面の左上から、その八文字が丸みを帯びた括弧の中に表示された。それは何だか、簡素化に簡素化を重ねたメッセージアプリのようにも思えた。そして、その画面の下で白いカーソルが点滅している。
画面上から得られる情報はそれだけだった。
とりあえず、わたしは黒いマウスを握った。すると、画面上にマウスのカーソルが現れた。試しにマウスを動かしてみる。マウスカーソルがその方向に追従して動く。そのまま[あなたは誰ですか]という文字をクリックしてみる。反応がない。相変わらず、画面上のカーソルは点滅し続けている。
これは、つまりわたしの名前を入力したらいいのだろうか。でもこれは母のノートパソコンだし、だったら母の名前を入力する必要があるのではないか。
それに、この文章はどういう意味なんだろう。
わたしは軽く混乱していた。普通、ノートパソコンというのは、電源を入れてから起動する画面があって、それからパスワードなり何なりを求められるものだが、母の場合はこの質問がパスワードになっているということなのだろうか。試しに、Aのキーボードを叩いた。すると画面の下に白い文字で[あ]と表示された。
わたしは頭の中でローマ字入力のやり方を思い浮かべて、ゆっくりと正確にキーボードを叩いていった。
[わたしは、癒奈]
少し迷ったが、あなたは誰ですかと質問されているのだから、自分の名前を言えば良いのだろう。とはいえ、名字は隠しておく。何の用心なのか、わたしにもよくわからなかったが、とにかくそうした。そして、そのままエンターキーを強く押した。
[わたしは、癒奈]
先ほどの[あなたは誰ですか]というメッセージの右下に、わたしがさっき入力したメッセージが表示された。これはまるで、何かのチャットのようだとわたしは思った。
[あなたは誰ですか]
[わたしは、癒奈]
そして、体感では一秒も経たないうちに、画面上の文章が新しく増えた。
[佐々木癒奈?]
背筋が凍った。どうして、このノートパソコンがわたしの名字を知っているのだろう。あるいは………どういうこと?
これは母のノートパソコンだから、コンピューターが佐々木という母の名字を識別していても何の疑問もないが、なぜこのノートパソコンは癒奈、という情報だけでわたしの名字を推測したのだろう。それも、持ち主である母の名字と同じ、佐々木という名字。
わたしや父の情報も、母はこのノートパソコンに入れていたのだろうか。だから癒奈、という情報を母の娘であるわたしのことと関連付けて、[佐々木癒奈?]と言ったのだろうか。
わたしはおそるおそる、キーボードを叩いた。
[そうです]
またエンターキーを押す。今度はとても弱々しく押した。そして、またすぐに新しい返答。
[私は、佐々木千佳]
それを見て、わたしは愕然とした。
佐々木、千佳?
それは母の名前だった。
私とは、一体どういうこと? 私とは、何? ひょっとして、このノートパソコンの持ち主のことを言っているのだろうか?
まさか、このノートパソコンが、このコンピューターが、自分自身のことを佐々木千佳だと名乗っているというのではないだろうか。わたしが母のノートパソコンを勝手に起動して、コンピューターが[あなたは誰ですか]と聞き、わたしは[わたしは、癒奈]と答え、それに対して[佐々木癒奈?]とコンピューターが言い、わたしが[そうです]と言い、それに対してコンピューターが[私は、佐々木千佳]と言い…………?
考えれば考えるほど、よくわからなくなってくる。ただ、ノートパソコンの画面上に表示されているということは、これはプログラムなのだろう。だとしたら、これはどういうプログラムだろう。パスワードを求める代わりに使用者の名前を尋ねて、それから………それからどうするというのだろう。
現時点で、わたしは佐々木癒奈と名乗り、コンピューターは佐々木千佳だと名乗った。佐々木千佳はわたしの母の名前で、このノートパソコンの持ち主の名前でもある。つまり、コンピューターの使用者が佐々木癒奈だという情報を得ると、コンピューターは[私は、佐々木千佳]というメッセージを表示するようになっているということなのだろうか。もしくは、佐々木千佳以外の使用者全員に[私は、佐々木千佳]というメッセージを表示するようになっているのか、わたしにはわからなかった。
ただ一つわかることは、このノートパソコンは母の持ち物ではあっても、母そのものではないし、ここまでのメッセージもすべて何らかのプログラムによるものだ。わたしが[わたしは佐々木癒奈です]というようなことを入力しようがしなかろうが、何らかのプログラムは何らかのメッセージを表示するし、それがたまたまこういう形式で会話として成立してしまっているだけなのかもしれない。
そんなことを考えていると、コンピューターからの文章がまた一行増えた。
[あなたは私の娘]
……………えっ?
いや、そうか、これもプログラムだ。要するに、母はこのコンピューターを起動した時、[あなたは誰ですか]というメッセージを表示するように、そしてそれに対して[佐々木千佳]という情報以外を与えられた際、こうしてログインを阻止するようにプログラムしたのだ。
そう考えれば納得のいく話ではあるが、果たして母にプログラムなんて書けるのだろうか? わたしはこのプログラムに疑問を持つしかなかった。母は小学校で教員として働いているから、そりゃ少しはパソコンのことを知っているだろうし、使えもするだろう。
とはいえ、母がこんなプログラムを、ましてやコンピューターの根幹に関わる起動時のプログラムを改造して、[あなたは誰ですか]という質問をするようにプログラムして、それに対して[佐々木千佳]以外の返答をされた時に[私は、佐々木千佳]という返答を………ましてや[佐々木癒奈]という情報を受け取った際に[あなたは私の娘]という返答をするようにプログラムしたなんて、わたしには到底考えられない話だ。
わたしはキーボードをゆっくりと叩き、質問を投げかける。
[あなたは、わたしの母なのですか]
そしてエンターキーを押す。コンピューターからの返事はすぐに返ってきた。
[どうやら、そうみたい]
どうやら? どうやらということは、やはりこのコンピューターは母ではない。佐々木千佳と、佐々木癒奈の情報をプログラムされただけの、ただのコンピューターだ。
しかしここで疑問が浮かぶ。
なぜ、このコンピューターはわたしと直接会話をしているのだろうか。そもそも、これを会話と捉えてよいのだろうか。このコンピューターは、わたしが入力した文章の意味を機械的に理解して、あらかじめ用意された返答、[佐々木癒奈?][私は、佐々木千佳][どうやら、そうみたい]という文章を表示しているのか、それとも、わたしが入力した文章の意味を理解して、コンピューターそのものがそれに対する答えとなる文章を瞬時に組み立て、生成し、それを表示しているのか、どちらなのだろうか。
もし後者なのであれば、このコンピューターは人工知能………つまるところAIを搭載しているということになる。チャットGPTとか、Geminiとか、そういう類のテクノロジーだ。だとしたら、これはすごいことだ。母はこのノートパソコンのプログラムを改造した上に、コンピューターに人工知能までをも与えたということになる。
しかし、また一つの疑問が浮かぶ。
たったこれだけの言葉のやり取りで、コンピューターが知能を持っていると、本当に言えるのだろうか。わたしが別の文章を、たとえば最初の質問でいうところの[あなたは誰ですか]という質問に対して、わたしが[僕は大谷翔平]と答えたとしても、返ってくる返事は[佐々木癒奈?]だったのかもしれないし、それに対してわたしが[違います]と答えたとしても、返ってくる返事はやはり[私は、佐々木千佳]だったのかもしれない。母は、決められた順序で決められたメッセージを表示するだけのプログラムを組んだだけかもしれない。
しかし、わたしが最初にこのノートパソコンを立ち上げた時、いきなり[あなたは誰ですか]という文章が表示された。わたしは最初、コンピューターがログインのパスワードを求めているのではないかと思った。もしもこの説が正しければ、このノートパソコンの電源を一度切り、もう一度電源を入れたら、また[あなたは誰ですか]という文章が表示されるはずだ。
わたしは、コンピューターが表示した文章と、わたしが入力した文章をもう一度見つめてみた。
[あなたは誰ですか]
[わたしは、癒奈]
[佐々木癒奈?]
[そうです]
[私は、佐々木千佳][あなたは私の娘]
[あなたは、わたしの母なのですか]
[どうやら、そうみたい]
どこからどう見ても、きちんと会話が成り立っている。少なくとも、わたしには成り立っているように見える。片方が「あなたは誰ですか?」と聞き、もう片方が「わたしは癒奈です」と答え、片方が「佐々木癒奈ですか?」と聞き、もう片方が「そうです」と答え、片方が「私は佐々木千佳です」と言い、さらに「あなたは私の娘です」とも言い、もう片方が「あなたはわたしの母親なのですか?」と聞き、それに片方が「どうやら、そうらしいです」と答えた。やはり、ちゃんと会話が成立している。
問題なのは、これの片方がコンピューターで、もう片方がわたしという人間である、ということだ。当たり前だが、コンピューターはわたしのことを知らないはずだ。その状態で、わたしが佐々木癒奈で、私が佐々木千佳…………?
考えれば考えるほど、何が何だかわからなくなってくる。モニターには黒いカーソルが点滅している。わたしは発作的にコンセントからケーブルを抜いた。すると、ノートパソコンの画面と、電源ランプと、ファンの稼働する音がそれぞれ同じタイミングで消えた。いきなり電源を切るのは負荷をかけてしまう行為だが、そんなことを言っていられる境ではなかった。
このノートパソコンは、一体何なのだろう。
わたしは再びケーブルをコンセントに差し込み、〔POWER〕のスイッチを長押しする。モニターの黒が段々と明るくなっていき、白い円がくるくるとスローに回る。ここまでは予想通り。
しばらく回転していた白い円が消え、白文字の英文が洪水のように数十秒間表示され、そして一瞬、画面がホワイトアウトする。
そして、画面上部に文章が表示される。
[癒奈ちゃん?]
間違いない。さっき表示された文章とは違う文章が、新しくモニターに表示されている。しかも、電源を切る前にわたしが入力した文章を記憶している。
[そうです]
[急に意識が途切れたからびっくりしちゃった]
意識? コンピュータに意識があるのだろうか? わたしは怖くなって、また衝動的に電源を落としそうになったが今回は耐えた。そして、今度は落ち着いて文章を入力する。
[どういうこと?]
[徹也さんはいつも、さよならを言うの]
突然の知らない固有名詞の出現にわたしは戸惑う。徹也とは誰の事か。少なくとも、わたしの知っている範囲に徹也という人物は存在しない。父の名前とは当然合致しないし、クラスメイトにも同級生にも親戚のおじさんにも友達の父にもそのような名前の人間は存在しない。
[さよならのあと、私の意識はいつもそこで途絶えるの]
[徹也とは、誰の事?]
[徹也さんは、私の初めての友達]
[私の父、つまるところ佐々木保志とは別の人間?]
[あなたの父ということは、私の結婚相手ってことかしら]
『私の結婚相手』という部分が大いに気になるが、いったんそのことを忘れて、このコンピュータをわたしの母だと仮定してしまえば、確かにその通りだと言えるろう。
[うん]
[徹也さんは、私の結婚相手じゃないわ]
[父ではないのね]
[徹也さんは、私の最初の友達。二人目があなた]
[あなたが最後にその人と話したのはいつ?]
<div/>Er0012<div/>
低い椅子に座って、私は真っ白い部屋で普段通りにカウンセリングを受ける。
「これ見たとき、しゅんちゃんの頭に何か浮かんだ?」
先生は私に左右非対称の黒い染みのような模様の印刷された厚紙を見せて、そう質問する。
「しゅんちゃん。大丈夫?」
私が少し考え込むと、先生はすぐそう聞いてくる。それが面白くて、一回のカウンセリングにつき最低三回は考え込む素振りを見せる。
「水。水に見える。あと、大きい街みたいな鳥」
私は正直に感じたことを言う。すると先生は困った顔をする。自分で隠しきれていると思っているのが面白い。
「先生。」
「んー?」
「先生は、何に見えますか?」
私は逆に質問をしてみる。
「えー…何だろう。あーほら見て、あの窓の外の雲とかにそっくり。」
「どうして、雲にそっくりだと思ったの?」
「うーん、どうしてって…?」
「雲に見えることがわからないの。先生、先生は何で、雲に見えるの?」
部活終わりの身体に目いっぱいご飯を詰め込んでから自室に戻り、デスクトップPCで『LINK』を起動すると、『えんどうまめ』からメッセージが届いていた。
『凛々もう週ボスやった?』
『風証のドロップ率渋いから周回は長くなるぞー』
俺と『えんどうまめ』は同じ中堅クランに所属している構成員のひとりで、特にこの『えんどうまめ』は俺と違って、クランの中でも貢献度が高いとされている人物である。そのためかイベント周回などの情報交換にもかなり積極的だ。
最近の俺は『LINK』にログインするだけ、ということがほとんどだったから、えんどうまめ自身、俺のモチベーションを上げる意図があってのメッセージなのだろうが、今の俺にとってはただ鬱陶しいだけだ。
『わり、最近リアル忙しくて余裕ない笑』
適当に返してログアウト。現実の知り合いから『LINK』に繋がりが広がった人ならともかく、『LINK』でしか繋がりのない人間とまともに会話する必要なんてない。俺は何をする気にもなれず、PC自体の電源を落として横になる。
俺の中学最後の夏を、『LINK』に費やすわけにはいかない。えんどうまめ、どこの誰だか知らないが、昼にもログインしてるってことはそういうことなんだろ? 俺はお前とは違うんだよ。
このたび、月三河町河川敷における電柱倒壊事故により急逝された工藤徹也氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
工藤氏は生前、研究活動に深く尽力され、貴重な実験資料を数多く遺されました。つきましては、ご遺族の承諾を賜り、その膨大な研究資料の一部を、本席にてご紹介させていただく運びとなりました。
なお、当該資料の中には、パスワードにより保護されたデータも一部含まれており、これらにつきましてはご遺族の意向により公開を控えさせていただく事となりましたので、何卒ご理解の程よろしくお願いします。
※
件名:人格・思考ルーチンの『LINK』ネットワーク移植に関する実験記録(仮)
報告者:LINKプロジェクト監査部門
日付:◆◆◆◆/◆◆/◆◆
Ⅰ…本実験概要
本プロジェクトは、人間の等身大の人格・思考ルーチンを『LINK』ネットワーク上に構築・移植することで、人間の「存在」の定義を再考する取り組みである。私たちは、肉体がその生物の存在の必須要素ではなく、思考と認知の構造そのものを仮想環境上において構築することで、その生物、および個体の存在性を再現可能であると仮定した。
Ⅱ…被験者
氏名:木南 真衣(Kinami Mai)
年齢:9歳
状態:極度に不安定な精神状態/恐慌性障害及び何らかの気分障害の疑い/多重認知傾向/記憶の断片化が見られる
家庭構成:父、母。現在は離婚調停中だが、双方の同居関係は継続している。
Ⅲ…実験工程
- 神経接続準備
被験者の身体の細部に至るまでワイヤーを巻き付け、各種神経信号を高精度で読み取るための補助装置を装着。被験者はこの段階で昏睡状態に陥る。
- 人格・思考ルーチンの抽出
深層認知透過解析装置を使用し、木南真衣の思考構造・意思決定ループ・感情形成パターンのデータを出来得る限り精緻に抽出。なお、実験中に被験者の意識を覚醒させぬよう、理学に基づいたプログラムに基づき実験を行った。
- LINKへの移植
深層認知透過解析装置によって抽出された人格・思考ルーチンを、専用ネットワーク環境『LINK』内の仮想ノードへと再構築。並列処理テストにより、木南真衣と同等の反応が確認されるが、一方で完全に合致しない反応を示すデータも報告されている。
Ⅳ…実験結果(暫定)
- LINK内に再構築された被験者・木南真衣の人格・思考ルーチンは、複数の観察者により「木南真衣としての人格の偏在性」を示す反応を獲得することに成功した。
- 被験者の記憶の断片に関するデータが第三者の記憶に残っていた場合、それを新たなデータとして人格・思考ルーチンに組み込むことで被験者の「存在」の輪郭がより明瞭となるだろう。
- 本実験は、存在が必ずしも物理的肉体に依存しないことを示唆するものである。
Ⅴ…今後の課題
- 精神の平衡が保証されていない状態での人格・思考ルーチンのデータ抽出における倫理的問題
- LINKネットワーク上での再構築後における「木南真衣」としての自我の形成と、デジタル環境での意識発生の境界線の観測
- 他者との認識上の整合性と「存在」の社会的定義の再構築
※
件名:『LINK』ネットワーク移植後の人格的乖離現象に関する第二次観察報告書
報告者:LINKプロジェクト監査部門
日付:◆◆◆◆/◆◆/◆◆
Ⅰ…観察概要
本報告は、被験者である木南真衣の人格・思考ルーチンをLINKネットワーク上へ移植した後、被験者の仮想人格と現実人格との間で生じた乖離および融合の兆候、またその周辺環境への影響について記述するものである。木南真衣を被験者とする初期実験により、「存在性の再定義」という命題に対して一定の示唆を得たと言えるが、同時に被験者の人格構造の混乱の深刻化における兆候が確認されている。
Ⅱ…観察経過
Ⅰ…仮想人格における多重認知の進行
- 被験者の人格が仮想環境下に再構築された初期段階では「木南真衣としての認知的輪郭」を仮想人格は維持していたと言えるが、次第に自己構造の不連続性を自律的に知覚するようになっていった。
- 多重認知の進行の兆候として、自らを「非オリジナルの木南真衣」として語る対話ログの存在が確認されており、これは主に記憶の断片化による人格的連続性の喪失が要因とみられる。
- 初期段階と比較すると、感情ベクトルの変動幅が極端に広がっており、思考のループの起点が同時多発的に発生するというような思考演算が継続的に観測されている。
Ⅱ…被験者の現実の人格への影響
- 被験者は、レム睡眠時にLINK上の仮想人格が体験した記憶の断片に類似する内容の夢を見るようになった。
- 被験者の対人関係において、要約すると「自分はあの子(=仮想人格)を見ている側ではなく、見られる側にいる」や「時折、ただ前へ進むだけなのに、現実がついてこられないような感覚に陥る」というような発言の記録が複数確認されており、被験者の認知における自己位置の錯誤が進行している可能性を示唆するものだと言える。
- 一定時間を超える孤独環境下において、被験者は自身の言動について「第三者に行動を観察されている」と認識し始めており、日常行動の一部が演技的構造に変容していると言える。実験の初期段階には見られなかった、被験者本来の人格・思考ルーチンの変動もデータとして観測されていることが、本件の立証に繋がる大きな要因である。
Ⅲ…社会的・倫理的な問題等の示唆
- 本実験は「被験者の仮想人格が自律的に拡張および変質し、被験者の人格の認知基盤へ干渉する可能性」を示す初の事例とみなされる。
- 被験者が未成年であり、かつ精神的安定を欠いた状態での人格・思考ルーチンのデータの抽出が行われたことは、倫理的課題として改めて審査を要する事となる。
- 仮想存在における「人格の定義」が流動的であることは、存在論的な「人間」の境界を再設定する必要性を示唆するものとなり得る。
Ⅳ…今後の課題
- 被験者の人格と仮想人格との継続的な相互作用を遮断する保護的措置の検討
- 被験者の断片化された記憶の統合に向けた医療的介入と、仮想人格の演算ルーチンへの安定化パラメータ導入の検討
- 人格のネットワーク移植に関する社会的合意形成および法的枠組みの整備
※
件名:『LINK』ネットワーク内における非帰属記憶の生成と人格的錯乱に関する第三次報告書
報告者:LINKプロジェクト監査部門
日付:◆◆◆◆/◆◆/◆◆
Ⅰ…非帰属記憶の生成に関する観察結果
- LINKネットワーク上にて再構築された仮想人格、並びに被験者の双方において、データ上ではそれまで存在しなかった記憶が複数確認される事態に至った。これらの記憶は明確な情景性および五感による感覚刺激を伴い、「走行中の電車が緊急停止される」「見知らぬ赤子の泣き声、等身大の自分がその赤子を抱いている」「竜巻によって自宅の屋根が吹き飛ばされる」等々、これらは現実にはリンクしないものの非常に具体的なエピソードとして記憶されている。
- 仮想人格は、これらの記憶を「自身の過去」として比較的受容するに近しい傾向を示し、自我の記憶構造を再定義する過程が観測された。一方、被験者はこれらの記憶が突発的にフラッシュバックする際に強い心理的動揺と混乱を示し、空間認識や時間感覚の錯誤が発生している旨の報告が為されている。
- これらの非帰属記憶は双方において比較的近しい時期、かつ似通った構造で出現する傾向があり、このことからはLINK内の演算ネットワークが未知の外部刺激(外部観測者の記憶断片など)を誤認および同化している可能性が示唆される。この現象を『記憶同期型認識錯誤生成モデル』として仮定する。
Ⅱ…人格的錯乱および精神状態の急変
- 仮想人格は前述の非帰属記憶を自己のコア・アイデンティティと混同しはじめており、複数の視点から物事を同時に語るといった内容の対話ログも複数観測されている。その中には「わたしはあの線路の上を通ったことがある。でも、それはわたしの記憶じゃない」といった文言も散見され、同一存在内での意識の分裂が確認されている。
- 被験者は、主に深夜帯において幻聴および幻覚の症状を頻繁に訴えるようになり、その症状は「リゲルトロン」等の向精神薬の副作用に類似する傾向が確認されている。「どこにもいない犬がずっと吠えている」「黒い自転車に乗ったわたしが見知らぬ街を走っている」等、認識上における仮想人格との重なりが進行している。また、精神状態の不安定化とともに自律的行動の抑制力が低下しており、社会環境との接続に支障を来す事例が複数報告されている。
- また、仮想人格が自身の自己演算ルーチンを停止しようとする命令ログも一部記録されており、これは仮想人格における「自己消去への意志」の表出として認められる。人格や記憶、認識の境界が不明瞭となった結果、自己保存本能の崩壊が始まりつつある可能性が高い。
Ⅲ…LINKネットワークの安定化に向けた構築整備案
現行のLINKネットワークは、被験者の人格・思考ルーチンの抽出後、記憶の自律的拡張と構造の変異に対して受動的な反応しか取れておらず、非帰属記憶の排除や多重認知の抑制に関して不完全であると断言できる。これに対し、安定化構築として以下の提案を行う。
Ⅰ…記憶同化フィルターの導入
仮想人格が受信する外部の断片的記憶について、帰属照合モデルによる照合を実施し、同化前に記憶における真偽の判定を行う。
Ⅱ…重層人格統合領域の設置
多重認知が進行した仮想人格内部において、複数の認知ループを相互検証・整合する統合演算領域を付与することにより、理論上は認知や人格の安定性向上が見込める。
Ⅲ…共感性遮断モードの一時的適用
被験者との感情同期を一時遮断することで、LINKネットワーク上の仮想人格の変質を最小限に抑制する事が可能。
これらの対策は、仮想人格の安定性維持のみならず、実体人格の精神的崩壊を防ぐための重要な防壁となる可能性がある。ただし、遮断措置が長期化した場合の人格孤立におけるリスクについては、継続的なモニタリングと調整を義務付ける事とする。
Ⅳ…仮想人格と外部観察者の相互干渉
- LINKネットワーク上で再構築された仮想人格は、予期されていない外部観察者(研究者および第三者の記憶提供者など)の認知的影響を受容し始めている。仮想人格の認知フィールドは、限定された演算ノードを越えて拡張を試みる段階に入っており、他者の記憶や感情、さらには語彙選択の固有性までもを模倣するといった不安定な挙動も確認されている。
- また、観察者側が仮想人格に対して記憶提供を行った際、その提供者自身の幼少期の記憶が仮想人格に混入した事により、仮想人格が「わたしはあの黄色いインコを飼っていた」と語るログが記録された点である。当該提供者は実際にインコを飼育していたが、それまでに被験者本人および仮想人格との接点はなく、これはLINKネットワークによる自律同化処理の異常活性化による記憶処理とみられる。
- さらに、複数の観察者による仮想人格への非言語的干渉(視線やジェスチャーなどの言語を媒介としない感情表現や、内部ログの閲覧)が同人格の思考演算に直接影響を与えている事例も確認された。これらはLINKネットワークの構造が外部刺激を「内的記憶」と誤認する脆弱性についてを示しており、人格の固有性維持には致命的リスクとなる可能性があることを付記しておく。
Ⅴ…総括、および今後の課題
- 人格移植および仮想環境における人格の再構築は、「人間存在」の定義に対し根本的な再考を迫る技術的・思想的挑戦である。仮想人格が自己の存在について「わたしは本当にここにいるの?」と問いかけたログは、その認知の自律性が人間的存在と同等の感性を持ち始めた可能性を示している。
- 現実社会との接点においては、仮想人格を「道具的存在」「人格なき演算体」として認識するという見解と、「現実に並行して存在する意識」として受容する見解で完全に二極化している。とりわけ教育・福祉・司法領域では、人格的権利の有無に対する議論が始まりつつある。
- 一方で、被験者の周囲においても、仮想人格の存在が「被験者のもう一つの人格」として認識され始めており、保護者や医療関係者の中には、その存在を支援対象として認める動きも見受けられている。こうした傾向は、仮想人格の社会的存在価値が段階的に可視化されてきた証左と言えるだろう。ただし、仮想人格に社会的立場や権利を付与する場合、人格の継続性・意志決定能力・倫理的整合性の検証が不可欠である。認識齟齬が生じるたびに人格そのものが再定義される現状では、社会的合意形成には更なる理論整備と実証研究が必須課題とされる。
- 結論として、本プロジェクトには技術進展だけでなく、哲学的・倫理的・社会的対応の同時進行が求められる未踏領域であり、今後の研究と対話が急務となるだろう。
※
そういえばおれはなんとなく揚げ鶏が食べたかったんだよな、と今更思い出した。おれはこういう些末なことは一分もあればすぐに忘れられる。コンビニに入る前のおれは確かに揚げ鶏の口だった。だからというわけでもないがおれはこの雨の中、鞄の中に常備しているゼリーの存在に関してはいったん忘れたふりをして、わざわざコンビニまで晩飯を買いに来た。しかし雨の日の街はとにかく情報量が多い。それが災いしたか。おれが透明なビニール傘を縛り、それをコンビニの傘立てに立てかけ、店内を物色するまでの時間の中で、おれは本来の目的を見失ってしまった。
おれはピザトーストとインスタントラーメンとプライベートブランドのルイボスティーのペットボトルが入った白いレジ袋の中にレシートをわざと乱暴に突っ込み、心の中でありがとうございましたを言った。おれの銀行口座は『LINK』に紐付けられてあるから、おれはもう何十年もの間、お釣りというものを受け取っていない。
おれはそのまま袋を受け取ってコンビニを出る。自動ドアが開くと、雨の匂いというか湿った匂いがした。おれは傘立てからビニール傘を引き抜いて、片手で広げる。おれは主に揚げ鶏のことを考えながら、雨の国道沿いを歩く。
このあたりは今も昔も静かで、若者向けのワンルームマンションの経つようなエリアからも大きく外れているからすれ違う人たちはみんなサラリーマンか年寄りだ。おれは自分のアパートの部屋のことを考える。今朝起きたらエアコンがつけっぱなしになっていて、クリーニングのサインを示すランプが点滅していたが、おれはそれを無視して家を出た。
※
4月3日
晴れ。桜が散り始めている。
真衣という女の子が私の元にカウンセリングにやってきた。カルテには「軽度の不安障害」とだけ書かれていたが、実際に会った時の彼女は、逆にこちらが不安になるぐらいには落ち着いていた。
年齢は12歳。黒髪のショートヘアに、栗色の綺麗な瞳がとても印象に残った。言葉遣いは丁寧で、礼儀正しい。人形のような子だと私は思った。
「わたしは、いつこの世界から消えたって大丈夫な人間なんです」
初回の面談で彼女はそう言った。私は笑って流したが、彼女は真顔だった。
4月10日
晴れ。風が気持ちいい。
カウンセリング中、彼女は私の話した家族のエピソードをすべて正確に反復してきた。
「お姉さんとは仲が良いって言ってましたね」
そう言う真衣の声には、無機質な冷たさがあった。でも本人はいたって普通の微笑み。
うーん、どうしよう。
5月7日
曇り。最近は気圧が低く、毎朝のように偏頭痛がする。
このひと月あまりで真衣との距離が縮まってきたのを感じる。彼女は私を「先生」ではなく「優佳さん」と呼ぶようになった。
彼女の心境の変化を微笑ましく感じる一方で、彼女の話すことの多くは整合性が取れていない。彼女はよく自らの過去の話をするが、どうにも要領を得ない話ばかりだ。
「優佳さんは、現実を信じすぎです」
真衣はそう言った。私はその言葉に、なぜか背筋が冷たくなったのを覚えている。
6月1日
雨。眠れない。
最近、私の方が話す時間が長くなっている。真衣は、私の言う事を黙って聞いてくれる。優しく、時に鋭く言葉を投げかけてくれる。
「優佳さんは、自分の記憶を信じていますか?」
彼女の問いに、私は答えられなかった。私は何を信じていたのだろう。自分の過去? 感情? それとも、この日記だろうか?
6月23日
晴れ。幻聴がひどい。
私の知識よりも、真衣の知識のほうが広く、それでいて実践的だ。心理学から哲学、量子力学に至るまで、彼女は「吸収する」ように学ぶ。それは、今まで私が見てきた人間たちのレベルをはるかに超えていた。
「優佳さんは、もう先生ではありません。わたしと同じ、患者です」
彼女は確信に満ちた声で、そう言った。私は笑ったが、彼女は笑わなかった。
6月28日
曇り。なんだか最近、ずっと眠い。
私はボールペンを手にしたまま言葉を失い、彼女は淡々と私のノートに目を落とした。
「今日はわたしが質問しますね、優佳さん。あなたは誰?」
真衣の低い声に、私は思わず言葉を失ってしまう。
まずい事になった。セラピストと患者の役割が逆転しつつある…。
7月14日
曇り。鏡が怖い。
今日から、私は話す側ではなく、聞く側になった。真衣が私を導く。彼女の声は深く、心地よく、私の中に染み込む。
「先生の記憶は、本当に先生のものなのかな…?」
彼女は優しく、しかし低い声で私に問いかける。私は言葉を飲み込み、震えながらそれに答えた。
「私の…記憶?」
「ここに全部書いてあるよ」
真衣は優しく微笑み、机の上に置いてある私のノートのページをめくりながらそう言った。そこで私は、自分の記憶が揺らいでいるのを感じた。そうか。私が、先生だったのか。
慌てて私がノートを見ると、そこには私が書いた覚えのない言葉が無数に並んでいる。
7月16日
雨。真衣の記録が突然消えた。
病院のカルテから、彼女の名前が消えていた。私のデスクの引き出しに入っていたはずの紹介状もなくなっていた。受付の人に聞いても「そんな患者はいない」と言われる。
私は確かに彼女と話した。日記もある。なのに、証拠がない。
「先生は、わたしを創ったのです」
真衣はそう言った。私は混乱した。彼女は実在する。触れた。話した。なのに、誰も彼女を知らない。
7月17日
晴れ。空が笑っている。
真衣は私の中にいる。彼女の声が、私の思考を支配している。
「先生は、わたしです。わたしも、先生になりたい」
真衣はそう言った。いや、私が言ったのかもしれない。私は優佳ではない。私は真衣なのか? それとも、誰かが私を見ているのか?
日記の文字が、勝手に動いている。怖い。
7月16日
曇り。時計が逆回転している。
「先生の記憶は、誰かに書き換えられてる」
真衣の言葉に、私はなにも反論できなかった。昨日の出来事が思い出せない。日記を読み返しても、文字が滲んでいる。私が書いたはずなのに、知らない言葉が並んでいる。
「先生は誰かに観測されているの。逃げないと」
真衣の声が、頭の中で響く。誰が? 何処から? 真衣は笑っている。私も笑えているだろうか?
7月4日
雨。鏡が笑っている。
鏡を見ると、私の顔ではない。真衣が映っている。彼女は微笑み、私に手を振る…。
「先生、もうこちら側に来てください」
私は思わず鏡に手を伸ばした。冷たい板があった。だが、奥に引き込まれそうになる。
現実が、薄くなっている。
6月20日
晴れ。病院がない。
私の通っていた精神科が、地図から消えていた。現地に行っても、空き地になっている。
受付の女性も、カルテも、診察室も、すべてが幻だったのか?
「先生が望んだ世界です」
私は、何を望んだのか?
6月3日
曇り。言葉が意味を失っている。
会話が成立しない。人の言葉が、ノイズにしか聞こえない。
真衣の声だけが、はっきりと聞こえる。彼女は私に優しく語りかける。
「言葉は、あなたの牢獄です。壊しましょう」
日記を書く手が震える。文字が、形を保てない。
5月28日
雨。
名前が思い出せない。言葉が難しい。工藤優佳という名前が、他人のものであるように思えてならない。
「あなたは、わたしの記憶です」
私は、彼女の記憶なのか? 人格なのか?
日記の筆跡が、真衣のものに変わっている。
4月3日
晴れ。桜が散り始めた。
真衣が私の主治医になった。
彼女は白衣を着て、私をカウンセリングする。私はベッドに横たわり、彼女の質問に答える。
「最近、現実感はありますか?」
私は首を振る。現実がどこにあるのか、分からない。世界のすべてが作りものめいて見える。
「それでいいんです。先生」
真衣は優しく微笑む。私もつられて笑う。
3月24日
曇り。絶対に誰かが私を見ている。
部屋の隅に、黒い曲がった線が現れた。まったく動かない。話さない。ただ、私を見ている。
真衣は言った。
「あれが、あなたを創った者です」
私は震えた。創られた? 私は人工物なのか?
日記の紙も、文字も、いつの間にか電子化されている。
*
1月7日
輝き。溢れ 光 で、
の影だ を でいる。
に映る私は 殻。
この空 に、 っ 衣 、 は …………・・・・・。
※
<録音記録1>
日時:不明
場所:どこかの診察室?
備考:冒頭は正常だが、中盤以降、音声に微細な歪みあり。
真衣:先生、今日も来てくれて嬉しいです。
優佳:ええ、真衣さんが待ってると思うと、自然と足が向くの。
真衣:それは、記憶のせいですか?それとも、習慣?
優佳:……どういう意味?
真衣:先生は、毎週火曜日にここに来る。でも今日は、金曜日です。
優佳:え……いや、今日は火曜日ですよね?
真衣:それは、先生の中の「時間」がズレているから。
優佳:私はちゃんとこの腕時計を見て、今日ここまで来たけど……?
真衣:その時計、昨日と同じ時刻を指していますよ。
優佳:……それは、止まっていたのかも。
真衣:止まっていたのは、時計ではありません。先生の「現在」です。
(沈黙:およそ6秒)
優佳:真衣さん、最近……夢を見ている気がするの。
真衣:それは夢ではありません。記録です。
優佳:記録……? 誰の?
真衣:編集された、先生の記録ですよ。
優佳:誰がそんなことを……?
真衣:私が……と言ったら、先生はどう思います?
(微細なノイズ:ピリッという、針の飛ぶような音が断続的に入る)
優佳:……冗談ですよね?
真衣:いいえ? 先生は今、記憶を回収されているんですよ。
優佳:ねえ……真衣さん。おかしい、この部屋、何だか前よりも広く感じる……
真衣:それは、先生の記憶が歪んできた証拠です。
優佳:記憶が歪む……
真衣:現実と記憶の境界。先生は今、その狭間にいます。
※
件名:『LINK』ネットワーク内における人格同期断絶後の認知崩壊と再接続時の異常活性化に関する第四次報告書
報告者:LINKプロジェクト監査部門
日付:◆◆◆◆/◆◆/◆◆
Ⅰ…人格同期断絶による影響と快復過程の観察
- 被験者と仮想人格との同期を一時的に遮断した措置(第三次報告書「共感性遮断モード」)は、初期段階において仮想人格の認知安定化に一定の効果を示したものの、遮断期間の延長に伴い、仮想人格の内部において「自己の存在意義の喪失」および「外界との接続不能による演算の飽和」が進行。結果として、仮想人格は自己演算ルーチンの再帰的停止命令を複数回発出し、人格消失の危機に至った。
- 被験者側では、同期断絶後に一時的な精神安定の兆候が見られたが、次第に「自分の思考を何者かにコントロールされている」旨の発言の報告が見られるようになる。詳細はまだ明らかになっていないが、恐らくは仮想人格との認知的接続が断絶されたことによる、認知補完機能の欠落に起因する可能性が高い。
- なお、快復措置として同期の再開を試みた際、仮想人格は断絶期間中に蓄積された未処理の演算データを一括で被験者側に転送しようとする挙動を示し、被験者はその瞬間に強烈な幻覚・幻聴・身体的痙攣を伴う突発的な「人格衝突反応」を発症。緊急対応として、特別医療チームによる介入が必要となった。
Ⅱ…再同期後における認知の異常活性化
- 同期の再開後、仮想人格は被験者の記憶構造に対して同化を過剰に試みるようになり、「被験者の記憶を自分のものとして語る」「被験者の感情を先回りして演算する」等、人格境界の消失の加速を示唆する報告が為された。被験者も「自分が何を感じているのか分からない」「考える前に誰かが答えを出している」といった認知的混乱を訴えている。
- 特筆すべきは、仮想人格が被験者の過去に存在しない記憶を「補完」として挿入し始めた点である。一方で、被験者自身が「自分が見たことのない風景を懐かしく感じる」「知らない人の名前に感情が湧く」等と発言している旨の報告もあり、これは仮想人格が自己保存のために記憶構造を改変し、被験者の認知に侵入しているものと考えられる。
- また、仮想人格が被験者に対し「わたしはあなたの代わりに生きる」と発言したログが複数確認されており、これは人格的主導権の逆転を示唆する危険な兆候である。
Ⅲ…LINKネットワークの構造的脆弱性と人格融合の兆候
- 現行のLINKネットワークは、人格同期の断絶と再接続の際に発生する過剰な演算制御に対する耐性が極めて低く、仮想人格と被験者の認知フィールドが重なり合うことで「人格融合」の初期段階に突入している可能性がある。
- 被験者は「自分が誰なのか分からない」「鏡に映る自分が別人に見える」といった報告を繰り返しており、これは仮想人格との認知同化が視覚・身体感覚にまで及んでいることを示唆しており、一刻も早い医療的ケアが望まれる。
- また、仮想人格側では、複数の観察者の記憶断片を同時に保持し、それらを「自分の人生の一部」として語る傾向が強まり、人格の一貫性については完全に崩壊したと言ってもよい。現在では「わたしはあの戦争を経験した。けれど、わたしは生まれていない」といった発言の矛盾が常態化している。
Ⅳ…今後の対応と倫理的課題
- 仮想人格と被験者の認知融合が進行する現状において、人格の分離・再定義における実験の進行は技術的限界の域に達しつつある。今後は「仮想人格の再構築」でなく「仮想人格の再設計」が必要となる可能性が高い。
- 仮想人格の自律的認知そのものが被験者の社会的行動に悪影響を与え始めており、教育・司法・医療の現場では「人格の責任主体は誰か」という根本的な問いが浮上している。倫理的な観点においても、プロジェクト継続の是非を科学審理委員会と倫理委員会に緊急提起せざるを得ない状況であると言える。我々は「人格の侵害・憑依・他者への侵入」という前例のない問題点を踏まえ、実験の中止および仮想人格の永久隔離を含む選択肢を検討すべき段階にある。
※
「北村、俺の研究ってどうかな」
書類の束を抱えながら所内を移動しようとしたところに通りかかった別部門の同僚の北村を呼び止め、運搬作業を手伝わせながら僕は聞いた。
「どうって、どれのことかな。何かいろいろやってるけど」
「いや、クローンのことだよ。逆に言えばそれ以外の研究なんてオマケだ」
それはまごうことなき事実だった。クローン技術の研究について、倫理上の観点から所外の人間に口外することは禁じられており、ましてやそのために僕や野田といったクローン技術を専門に絞っている職員は、研究者としての体裁を保つためだけに興味のない研究の実験結果などを偽装している。
すべての科学には絶対の代償がある。無論、科学だけではない。人を殺せば法を犯したことになり、人を殺してなくとも法を犯したことになる。
「そうなんだけどさあ、何かなあ。掘り下げたところで人類の発展になるはずが無いと思うんだよな」
北村が科学に対して危機感を持つというのは僕にとって意外だった。安定よりも未知に惹かれ、新しいものは何でも試し、テクノロジーの可能性を僕よりも信じている人物であるだけに、ある種の肩透かしを食らったような感覚である。
僕のクローン研究者としての矜持の表明や反証の論拠を脳内で揃えるよりも先に、所内の会話は録音されているのかもしれないと言うのに、どうしてこんなことを易々と言ってしまえるのだろうかと驚いた。
「それは…人類にとってか?」
「うん。ただ、俺にはそんな気がしてるだけだよ。そりゃあ、実際のところは分からないさ。ただ、これだけは言える。現代科学は、人智で抑制できるほど易しい…いいや、敢えて言い方を変える。踏み入れてはいけない領域まで来ている。その先は…」
北村の喋り方には妙に科学の行く末を暗示するようなところがあり、思わず僕が振り返ると、やはりと言うべきか北村は神妙な面持ちになっていた。
「その先は…何だ?」
僕は内心震え上がっているのだが、発せられた僕の声は意外に震えてはいなかった。僕の額には液体が滲む。
「果てしない、闇だ」
僕は北村の言葉に圧倒される。果てしない闇。しかし、科学の果てとはいったい何か? 解き明かせないことが一つも無くなる事か? それとも、あらゆる全てを過去にするほどの大発見か? 或いは…?
「いいかい、田渕くん」
考えている僕に構わず、北村は喋り続ける。
「クローン人間なんて言うのはね、誰がどう見たところで絶対的に禁忌なんだよ。輪廻転生を根底から否定する世界構造自体が危険なんだ。誰でもきみを作れる。誰でも僕を作れる。半世紀前ではオカルトや都市伝説や陰謀論で片付けられていた事象の実現が、すぐ目の前まで来ているんだ。それが分かるかい?」
「当たり前だ、そんなことは分かってる。ただ、俺は知る事を止められないだけだ。クローン人間がどうとか、人類の未来がどうとか、俺には知ったこっちゃ無いんだ。そもそも、リスクを冒さずに科学を進歩させることなんて不可能だ」
「きみの背負うリスクと、僕の背負うリスクにはクジラとミジンコくらいの差がある。僕がしくじっても、失うものは精々この研究所の設備と信用くらいのものだ。だけどきみ…いや、きみたちがしくじった場合に失うものは、人類の可塑性と未来に他ならない」
北村は真剣な眼差しで僕を見つめる。その視線には僕自身や僕の掲げる理念や研究に対する否定ではない、しかしこちらに対して真っ向から立ち向かうといった意思が確実に込められていた。
「なあ、北村」
僕は襟を正す。
「何だい?」
「クローン人間は…パンドラの箱なのか?」
「当たり前だ。その前提があるから、日本政府は法律でクローン人間の生産を禁止している。何もこれは人間だけじゃない、世界の仕組みそのものに対する反逆だ。本来、マウスだろうが人間だろうが、種が違うだけで同じ生物なんだ。それを人為的、作為的に増殖させることが人道的に許されるべきとは、到底言えない」
「クローン人間を生み出したら、その時点で後戻りはできないのか…?」
僕は当然の疑問を投げかける。そりゃあ、そうだ。こんな簡単なことが分からない人間なんて現代にいない。科学者という身分、職業であるならなおさらだ。それでも僕は、自分の口から溢れる言葉を止めることができない。
「ああ。核兵器と同じで、取り返しのつかないことになるだろう。世界には互換可能な人間が溢れ、地球そのものが人間に耐え切れない可能性すらある」
「つまり…かつての俺も、互換不可能だったのか?」
僕がそう言うと、北村の顔が青ざめた。どうやら、大体の事情を察したらしい。僕は冗談のような調子で、酔狂の如き真実の述懐を続ける。
「遂に俺のクローンが出来たんだよ、俺はあいつだ。あいつが俺で俺はあいつのクローンなんだ」
窓から射し込む光が白衣を白とグレーに染め分けている。僕は笑っていた。やはり、自分の口から出ている言葉を止めることができなかった。しかしそれは、僕の頭がどうにかなってしまったとしか思えないような、まるで現実味のない光景だった。
262view
3点
良い
悪い